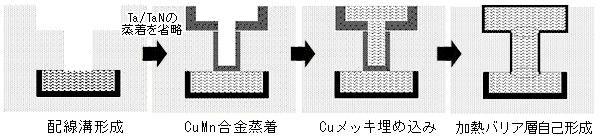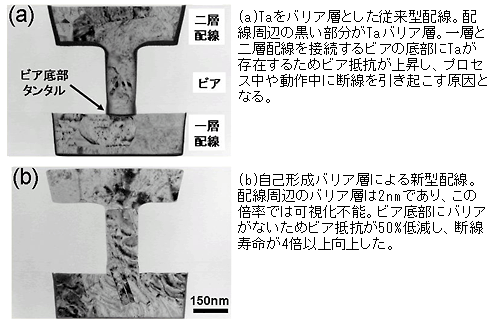PRESS RELEASE
2005/06/28マテリアル・開発系の小池教授等の研究グループは45nm世代対応のLSI配線プロセスを開発しました。
東北大学マテリアル・開発系の小池淳一教授と(株)半導体理工学研究センター(代表取締役社長兼CEO:下東 勝博、以下「STARC」)は、 45nm世代以降のLSI配線において、工程数が短縮でき、デバイス特性と信頼性をともに向上できる新規銅配線プロセスの開発に成功した。配線材料に銅マンガン合金(CuMn合金)を用いることで、配線と層間絶縁膜との界面に極薄(2nm)バリア層を自己形成し、実際のデバイス構造において実証した。これによって微細化に伴う配線抵抗の上昇と配線不良の問題点が一気に解決でき、45nm世代の実用化が加速するとみられる。
現状の90nm世代の銅配線プロセスでは、層間絶縁膜への銅の拡散を防ぐため、金属タンタルや窒化タンタルを銅と絶縁膜の界面に形成してバリア層とする必要がある。しかし、配線の微細化に伴い、狭い配線溝内にバリア層を形成することが困難となり、配線の信頼性が劣化することが懸念されている。また、バリア層の電気抵抗が銅に比べて二桁高いため、微細化に伴う配線抵抗値の急激な上昇によるデバイス性能の劣化が懸念されている。
この課題を解決するため、高抵抗バリア層の形成工程を完全に省略し、銅配線に添加した合金を界面に拡散させて絶縁層と反応させることによってバリア層を自己形成させるプロセスが検討されている。しかし、添加元素が銅配線中に残存して抵抗上昇をもたらしたり、バリア層の厚さが制御できないことや、銅との濡れ性が悪いなどの問題があり実現に至っていない。
今回、東北大学とSTARCの共同研究グループは、新規配線材料としてCuMn合金を開発し、配線の抵抗値を上昇させることなく極薄のバリア膜を自己形成することに成功した。用いたプロセスは、絶縁層に配線溝を形成した後に、バリア層形成工程を完全に省略し、蒸着法を用いてCuMn合金を形成し、溝の残りの部分に電解メッキ法を用いて銅を埋め込む。その後加熱処理を行なうことによって、マンガンを絶縁層の界面に拡散させてバリア層を自己形成する。
従来の配線構造ではタンタルバリア層の薄肉化が困難なため配線抵抗の低減に限界があった。また、一層と二層配線を接続するビアの底部にタンタルが存在するためビア抵抗が上昇し、プロセス中や動作中に断線を引き起こす原因となっていた。これに対して、新型配線構造の目玉となる自己形成バリア層は厚さが 2nmまで薄肉化でき、配線抵抗を純銅レベルまで低減できた。また、ビア底部にバリア層がないためビア抵抗が50%低減し、断線寿命が4倍以上向上した。
新しく開発されたプロセスを用いることによって、45nm対応の高性能・高信頼性配線が実現できるだけでなく、バリア層に高価な金属材料を用いる必要がないこと、バリア層形成工程を省略できること、現状のプロセス装置に適用可能であること、45nm以前の配線にも適用できること、などコスト的にも多くのメリットが期待できる。
【お問合せ】
東北大学工学研究科・工学部情報広報室
TEL/ FAX:022-795-5898
E-mail:情報広報室メールアドレス